科捜研の女は、1999年の放送開始から26年にわたり、科学の力で真実に迫り続けてきた長寿ドラマだ。
榊マリコを中心とする科捜研のメンバーは、最新の科学鑑定と地道な検証を積み重ね、数えきれない事件を解決へと導いてきた。
その積み重ねの先に描かれたのが、2026年1月23日放送のファイナルである。
本作は、単なる最終回ではなく「科学とは何か」「正義とはどこにあるのか」というシリーズを貫いてきた問いに、一つの答えを示す物語だった。
本記事では、最終回のあらすじを踏まえつつ、榊マリコが下した決断の意味、そして26年間続いた『科捜研の女』が最後に視聴者へ託したメッセージを考察していく。
科捜研の女ファイナルあらすじネタバレ
京都市内のスマート・モビリティ実証実験特区で、複数の自動運転機器が同時に暴走・爆発する事故が発生し、ロボット企業の開発部員の男性が死亡した。
事故か事件かを見極めるため、榊マリコ(沢口靖子)率いる科捜研は、現場に残された微物やシステム障害を科学的に解析していく。
やがて特区の集中管理システムへの不正アクセスが判明し、事件はサイバーテロの可能性を帯び始める。
捜査の過程で被疑者のDNAと指紋が検出され、中津琉剛(小林虎之介)が浮上するが、鑑定結果は一致せず、妹の琉葵(莉子)は兄の無実を信じて真犯人の特定を訴える。
マリコは犯人の顔を特定できるDNAフェノタイピングの使用を考えるものの、日本では違法鑑定にあたるため実行できず、葛藤を抱えることになる。
その後、琉剛は消息を絶ち、遺体となって発見されてしまう。
自らの判断を悔いたマリコは、土門薫(内藤剛志)に止められながらも禁じられた鑑定に踏み切り、ついに事件は解決へと向かう。
しかしその代償として、マリコは警察組織にとどまれない立場に追い込まれる。科学者としての信念を貫いた彼女は、科捜研を去り、新たな道を選ぶ決断を下すのだった。
科捜研の女ファイナル|なぜ榊マリコは違法と知りながら鑑定をしたのか
今回のファイナルで描かれた最大の転換点は、榊マリコが日本では禁止されているDNAフェノタイピングに踏み切ったことだ。
この行為は警察組織のルールに明確に反するものであり、決して正当化できるものではない。
しかしマリコの選択は、ルールを軽視した暴走ではなく「科学者として目の前の真実から逃げなかった」という姿勢の延長線上にあったと言える。
被疑者の顔を特定できていれば救えたかもしれない命。
その可能性を前に、マリコは科学を使わないという判断そのものが、結果的に誰かを見捨てる行為になり得ることを突きつけられる。
警察官としての立場と、科学者としての責務。その二つが決定的に矛盾した瞬間、マリコは後者を選んだ。
この選択は「正義」だったのか、それとも「過ち」だったのか。物語は明確な答えを示さない。
ただ一つ確かなのは、26年間一貫して描かれてきた榊マリコという人物が、最後まで科学者であろうとしたという事実だ。
彼女はルールを守ることで自分を守る道ではなく、科学の責任を引き受ける道を選んだ。その覚悟こそが、このファイナルの核心だった。
科捜研の女ファイナル|科捜研が最後に守ろうとしたもの
マリコの違法鑑定が発覚した後、科捜研の仲間たちは彼女を感情でかばうことはしなかった。
所長は処分を免除する道を選ばず、科捜研という組織そのものの「自浄作用」を働かせる決断を下す。
それは、仲間だから守るのではなく、科学者集団として正しくあろうとする姿勢だった。
注目すべきなのは、検証が徹底的に“鑑定”として行われた点だ。
マリコの行為は、好意や同情ではなく、科学的・論理的に評価される。
26年間積み重ねてきた科捜研の姿勢は、最後の最後で「感情より科学を優先する」という形で示された。
この構図は、マリコを切り捨てた冷酷な判断ではない。
むしろ、彼女が築いてきた科捜研の在り方を、仲間たちが最後まで守り抜いた結果だったと言える。
誰かを特別扱いしないこと、間違いを曖昧にしないこと。
その厳しさこそが、科捜研という組織の誇りであり、26年続いたシリーズが最後に示した一つの答えだった。
科捜研の女ファイナル|26年間で変わった科学鑑定と『科捜研の女』の到達点
『科捜研の女』の26年間は、そのまま科学鑑定の進化の歴史でもあった。
シリーズ初期に描かれていた鑑定は、顕微鏡や化学反応といった比較的シンプルな手法が中心で、科学は「補助的な真実」を示す存在だった。
しかし時代が進むにつれ、DNA解析やデジタル鑑定、AIによる予測技術などが登場し、科学は事件解決の“核心”を担うまでに進化していく。
科学が進歩することで、より多くの真実が見えるようになった一方で、同時に新たな問題も生まれた。
それは、科学が強力になりすぎたがゆえに「どこまで使っていいのか」という倫理の問題が避けられなくなったことだ。
DNAフェノタイピングは、その象徴的な存在と言える。
科学的には可能でありながら、社会や制度がまだ受け止めきれていない技術――それが、ファイナルで描かれた最大のテーマだった。
本作は26年かけて、科学の進化を無条件に礼賛することはなかった。
むしろ、科学が進めば進むほど、使う側の覚悟と責任が重くなることを描き続けてきた。
そしてファイナルで突きつけられた問いは「科学は正義になれるのか」ではなく、「科学を正義として使いこなせるのか」という段階にまで到達していたのだ。
科捜研の女ファイナル|最後まで「科学者」であり続けた理由
榊マリコが最後に選んだ道は、警察という肩書きを失う代わりに、科学者としての姿勢を一切揺るがせない生き方だった。
26年間、彼女が繰り返し口にしてきたのは「科学は正義のために使われるべきだ」という言葉だ。
その意味は、時代とともに少しずつ変化してきたが、根本にある信念は一度も変わっていない。
科学鑑定が飛躍的に進化し、真実により近づけるようになった今だからこそ、科学者には結果だけでなく、使い方そのものへの責任が求められる。
マリコはその重さを誰よりも理解していた。だからこそ、科学を使わないという選択で自分を守ることはできなかったのだと思う。
警察を去る決断は、科学と向き合い続けるために、自らの立場を手放す覚悟だった。
榊マリコは最後の最後まで、科学の力を信じ、その危うさも引き受ける科学者であろうとした。
その一貫した姿勢こそが、『科捜研の女』が26年かけて描き続けてきた核心だったのではないだろうか。
科捜研の女ファイル|まとめ
科捜研の女のファイナルは、事件の解決そのものよりも「科学とどう向き合うのか」を問い続けた26年間の到達点を描いた物語だった。
進化した科学は多くの真実を明らかにする一方で、使う側の覚悟と責任をより重くする。
その現実の中で、榊マリコは最後まで科学者として目の前の真実から逃げなかった。
派手な結末ではなく、静かな決断で幕を下ろしたこのファイナルは『科捜研の女』という作品が何を大切にしてきたのかを、強く印象づける終わり方だったと言える。
【アラカンサヲリのひとこと】
科捜研の女は、26年という長い歴史に幕を下ろしました。
本当に長く、多くの時代を共に歩んできたドラマだったと思います。
正義を貫こうとすればするほど、なぜか理不尽な結果に行き着いてしまう――そんな難しさは、現実の社会でも変わりません。
私自身、いまだにその答えを見つけられずにいます。
それでも『科捜研の女』は、科学を通して私たちに考える材料を投げかけ続けてくれました。
今回、榊マリコが見せた涙のシーンには、彼女自身が重ねてきた年月がにじんでいたように感じます。
感情を抑えてきたマリコが流した涙だからこそ、26年の歴史の重みが伝わる描写でした。
終わってしまうのは寂しいですが、心から――26年間ありがとうございました。
そして、本当にお疲れ様でした。
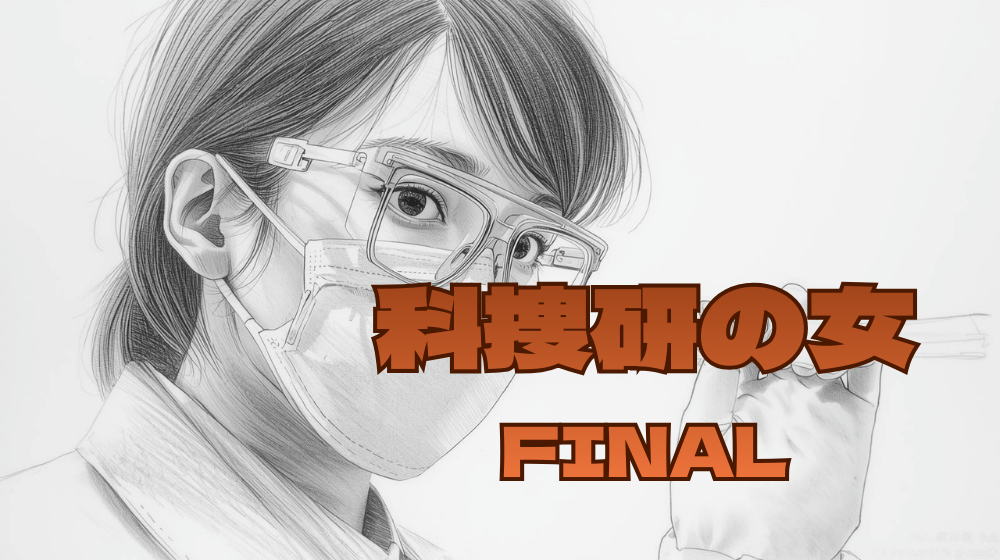


コメント